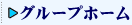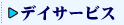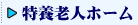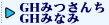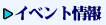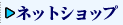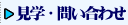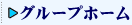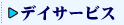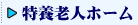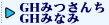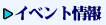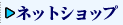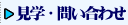| 記述と語り【2008.02】 |
|
宮澤 健
|
|
里のグループホームではケアプラン会議を毎月行う。ケアプランはグループホームに作成が義務づけられているのだが、里のこの会議はかなり特異なありかただと思われる。一般的には9人の入居者のケアプランを介護計画作成者ひとりが短時間で作っているようであるが、里では中心スタッフ4人が集まって話し合う。それぞれ担当を受け持っていて、その人について一ヶ月の動きや、入居から今までのプロセスを把握して、その人のテーマや、課題、今後の方向性、さらにはその人の背後に見えてくる社会や歴史を見つめる作業を、時間をかけて話し合う。 |
|

|
以前はこの会議はエンドレスで行われた。夜7時から始まって、終わりが深夜1時という事がざらだった。しかも終わった後も残って話が続く。草創期の手探り状態では、スタッフも意気が盛んでそうした勢いが違和感なく行われていたのだが、8年も過ぎる今では、勢いばかりではなく、洗練された時間の使い方も必要だと意識して、せめて10時には終わりたいのだが、どうしても11時になってしまうのが現状である。
なぜそんなに時間をかけるのかということだが、それぞれのスタッフが利用者個々に、かなり深いコミットメントをして、入っているので、客観的な記述では終われないという事情によるのだと思われる。記述は客観的に事実を書き並べる記録だが、一方、自分の感じたこと、心が動いたことも入れていくとそれは物語になってくる。物語は簡潔には語れない。エピソードや感覚、空気、雰囲気が重要な役割を持っているので話が長くなる。長いだけではつまらないので語っているうちに自然に深くなってもくる。時には延々と収拾がつかなくなってしまって、エンドレスになる。それをやっているのが里のケアプラン会議なのである。
現場は本来葛藤に満ちている所だ。その葛藤をどう捉えるかで、面白いか面白くないか両極端に別れる。つまりときめくか、さめるかに別れてしまう。
一般的には記述は科学的記述のことであって、そこに語りを持ち込むことは許されない。「個人的な主観は入れないように」という指導がされる。それはそれで普遍性を持つためには必要なことである。しかし現場にはそれで良いのかという思いが残る。 |
|

|
アメリカ在住の写真家、杉本博司は近代、現代を、光の文化−露出オーバーの時代だと言い、視覚の文化で影の消滅が特徴だと分析している。杉本博司の作品にハリウッド映画を二時間露出したままカメラにおさめたのがある。写真は真っ白になる。これが現代と言わんばかりの作品。光が当たりすぎて露出オーバーの時代。立体感のない平板化した時代をつくったのはあまりに強い光。その光は闇を照らすにはよかったが、闇を失うと闇の住人は行き場を失い世界の大半が消滅してしまうと、日本人の感覚で主張している。
光の文化は目の文化、視覚文化とも言える。そこでは味覚、臭覚、触覚、聴覚が使われにくくなって身体性が失われる。第六感の心は最も使われなくなる。それは人間が目指してきた便利の本質でもあって、表面的に解る、知るといことと、楽をするというのは人間の目指してきた近代化の結論だった。現代はその上澄みの中に生きている。
記録を書くとき、語りたいが語れず、ほとんど強制的に記述を強いられる現場がほとんどではなかろうか。おそらく福祉現場のほぼ全てが当たり前のように、疑うこともなく、語りを封印し、記述に終始しているのが実態であろう。中には個人的に語りを紡ぎ出してしまう人もいるはずなのだが、それは組織的に抹殺されてしまうのが現状だ。彼らの中には語りの代わりに、記述の文に、苦肉の策としてアンダーラインを引いているという人もいる。笑えない現場の個性の努力と抵抗がある。
里のケアプラン会議はこのアンダーラインの所を縦横無尽に語り深めあう作業をしているのだと思う。4時間という時間がかかっても、退屈や苦痛はない。入ってしまえば長く感じる事はなく充実の時間が蓄積していく実感がある。時間の短縮は念頭に置くにせよ、これからも語りを大切にしてやっていきたい。
|
|

|
|
|
|
|